環境活動家のテンダーさんは、生態系の再生と人びとの日常の困りごとの解決を同時に可能にする技術や仕組みを研究し、世界の人たちと共有しています。この連続講座ではその一部をおすそ分けしてもらいます。
といっても、ただテンダーさんの手法をなぞるわけではありません。一人ひとりが手を動かし、つぶさに観察し、得た情報と自分の知識を照らし合わせ、思考を働かせ、仮説をたてて実験することをたっぷり体験します。それは、お金や消費社会といった既存のシステムの構造を知っていく道のりでもあり、自分の生きかたをオルタナティブな視点から考える機会にもなるかもしれません。
▶︎ このオンライン講座の趣旨は「テンダーさんのその辺のもので生きるオンライン講座、はじまるよ!」をご覧ください。
*このレポートは、このオンライン講座シリーズ全体の講師、テンダーさんに執筆をお願いしました。
この回では、NVC(NonViolent Communication = 非暴力コミュニケーション)の考え方、有りように触れるために安納献さんと鈴木重子さんの2名の講師をお招きしました(お二人はNVCの公式トレーナーです)。
NVCは、いつ何時も怒ることのない聖人君子になるためのものではなく、
- 率直であること
- 感情やニーズ(深い願い)を等身大で表現できるようになること
- 物事に含まれている権威や使役の構造を理解できるようになること
- 「共感」という、哺乳類特有の他者とのつながり機能を復活させること
を目指しているように私テンダーは思っています。
このレポートでは、なぜ「その辺のもので生きる連続講座」にてNVCを取り上げたのかの意図を解説します。
目次
- NVC回 : 設計の意図について
A. 「その辺のもので生きる」は、技術のみで達成できる有りようではない
B. 暴力を「雰囲気」だと思っている人が多い - NVC回 : 当日の様子
1. NVC回 : 設計の意図について
A. 「その辺のもので生きる」は、技術のみで達成できる有りようではない
この連続講座を始めて、ちょうど全14回の折り返しにあたる頃、私は「何か足りないんだよな・・・」と感じ始めていました。
講座の参加者さんは非常に勤勉で、行動力もあり、講座自体は一見順調のように見えました。しかし、私の感じていた違和感を国際文化フォーラム(TJF)の室中さんと何度も話すうちに、だんだんとその正体が掴めてきたのです。
自分が今、暴力に加担しているという自覚があるか?
それは厳しい言い方をすれば現状で「自分たちが加害側であるという自己認識があるかどうか」です。
化石燃料や希少金属などの地下資源を「お金さえ払えば」自由に使える自分たちこそが、世界を、環境を、次世代の取り分を破壊しているという自覚があるのか。
その自覚なく、自給的な技術を身につけたところで、結局その成果は「的外れな亜種」に落ち着くということを私は経験則的に知っていました。
的外れな亜種: 電力自給をするために高価なリチウムバッテリーを大量に買ったり、トイレを自給しようとして地下水を汚染してしまったり。自分を越えたつながりへのまなざしを持たない限り、その自給暮らしは人間の傲慢さの域を出ることはありません。
ただし、この講座は中高生向けであり、環境活動家に向けたものではありません。
主義信条を突きつけて進退を迫る、というようなことはこの講座の目的ではなく、
そもそも糾弾したいのではなくて、次のことを理解をしてほしいのです。
その辺のもので生きることは目的ではなく、やり方(手法)なのです。
ではそのやり方で到達しようとする目的は何なのか、と言えば、
「暴力に加担しないために、その辺のもので生きる」のです。
その辺のもので生きるための前提 「遠くから持ってこない・遠くへ捨てない」
「その辺のもので生きる」の逆は、私が思うに「遠くから持ってくる・遠くに捨てにいく」となります。
「遠くに捨てに行く」については深く考えなくとも、自分のいらないものを自分とは関係のない(薄い)場所へ押し付けている感じがするので、なんとなく良くはなさそうです。
では、「遠くから持ってくる」は、何が問題なのでしょうか?
遠くから持ってくるとはつまり、「遠く」の「それ」が「遠く」からなくなることを意味します。
—
例えば、とても木目の美しい木があります。その木は加工もしやすく使いやすいので、みんなが欲しがります。
すると、お金になるので原産国からどんどん国外に輸出されます。
木の成長するスピードは木の都合で決まるのであって、人間の都合では決まりません。
どんどん伐れば木の成長は追いつかず、遠からず木は無くなっていきます。
ここまで来ると、システムの次の挙動が始まります。

手に入らないので、より木は高価になります。数が少なくなってしまったので法律で伐採を規制しよう、保護しようという動きが始まります。なぜならこの木はこの国の大事な「資源」なのだから。
伐れなくなった高価な木と、それにまつわる人々は、次にどんな挙動を生むでしょうか?
密猟です。
伐れなくなったために市場の流通数が減り、より高価になり、非合法なルートでの売買が始まる理由ができます。
規制側も黙って見ているわけにはいかないので、パトロールが始まり、争いが起き、人間の対立が生まれます。

Illegal mahogany extraction site, Texiguat Wildlife Refuge, Honduras. April 2008. CC BY-NC-ND 2.0
さて、以上の一連を引き起こす「それ(=美しい木)」を欲しい、ってなんだと思いますか。
露骨に言えば、自分が「それ」を手にするためには、苦しんだり嫌な思いをする人がいても構わない。
つまり「自分とその人は対等ではない(その人は嫌な思いをしても致し方ない)」という視点が存在すると、私は思うのです。
もちろん、近くだからといって問題が発生しないわけではありません。
しかし、「近く」の場合、逃げられなさによって「それ」とつながり、当事者として関係性を保ち続ける必要が発生するので、問題が悪化しにくいのです。
(ゴミを捨てれば自分の周りが汚れ、何かを消費利用すれば、その分、身の回りから何かが失われるのが見て取れるので、過剰には行わなくなる)
環境を破壊しない暮らしを選ぶ際に、対等性は非常に重要です。
対等性への理解こそが、あなたの一挙手一投足が暴力性につながるかどうかと、密接な関係があると私は思う。
そしてその対等性は、対人間のみに留まらず、生態系一連にまで思いを寄せることはできるのです。
私は、そのための手法として「その辺のもので生きる」を扱ってほしかった。
それが、NVC回を設定した理由の一つめです。
B. 暴力を「雰囲気」だと思っている人が多い
暴力とは何か?
さて、では一体暴力とは何でしょうか?
この講座では、鈴木重子さんが
「他人のニーズを満たさない言動を誰かがジャッジしたとして、そのジャッジの言葉が暴力 」
という表現をしました。
ここで私が非常に重要だと思うのは「たとえそのジャッジが賛美であっても、それは暴力だ」ということです。
仮に「あなたは素晴らしい」と言うとき、
- 「あなた」を評価できる自分は何者なのか?
- 何が素晴らしくて、素晴らしくないのかを断定できる自分は何者なのか?
- 以上2つを応用して、自分が「あなた」より上位であることを表現するために、「あなたは素晴らしい」と言うことができる。
- 「あなたは素晴らしい」という評価には賞味期限が設定されていないので、相手を「素晴らしい」状態に縛り付ける可能性がある(呪いの言葉に変わるリスクがある)
など、考えればいくつかの「おかしさ」が挙がります。
これまで褒められても受け入れ難かったり、違和感があった経験のある人は多いはず。それは「なぜあなたに褒められなきゃいけないのか?」だったり、「なんでいきなりマウントしてくるの?」といった、関係性に対する違和感なのでは、と私は思うのです。
つまり他者を評価するとき、「他者を評価できるという、より上位の自分」が設定されていて、それは対等性の関係性からは外れたものです。
それが良いとか悪いとかではなく、そこには暴力がありますよ、ということをひとまずご理解ください。
(もちろん、暴力の定義は上記のものだけではなく、自分が望まないのに他者から力を行使されれれば、それは暴力です)
補足: 相手を褒めたいとき
もし「あなたは素晴らしい」と言いたくなったときに非暴力的な表現をしたいのであれば、
「あなたの振る舞いを見たことで、私は(内的な欲求)を満たすことができて、いい気分だ。ありがとう」
というような言い方ができます。
- あなた=素晴らしい
ではなく、
- あなたの行動 → 私の自発的内部処理としての心の動き → その結果の良い感情 → この一連を伝えたい → ありがとう
というように、同一視の作法をやめて物事の連鎖を捉える視点を持てば、相手と自分は切り離された別個の人間として扱われ、評価の呪縛から逃れて相手に謝意を伝えられるようになります。
C. 非暴力を理解する段階
さて、長々と書きましたが、このレポートで私が言いたいことは大きく3つで、
- 本質的にその辺のもので生きるためには、対等性の感覚が必要(搾取に加担しないため)
- 対等性と非暴力は表裏一体
- ゆえに、その辺のもので生きるためには非暴力への理解も必要
ということです。
そして私が思うに、非暴力を理解し、実践できるまでに大まかに3段階あります。
レベル1 構造への理解
…言語や行動に含まれる暴力性や特権などを理解できる。
書くは易しですが、実際には文化上の暗黙の了解や、習慣なども含まれるため、実際につぶさに一つ一つ再認識するのは時間のかかる作業です。
特権の例: 日本では身体的男性の方が特権的であり、例えば横柄でも女性より許容されやすい(おじさんだから、で済んでしまう)。
日本に生まれ日本のパスポートを所持している時点で、世界の圧倒的多数の国よりも特権的に行動の自由が高い。
レベル2 振る舞いへの反映
…言語や行動に含まれる暴力性や特権などを理解したうえで、自身の行動から必要に応じて暴力性を排除することを目指せる。
「ねばならぬ」「させる」「しなきゃいけない」などの表現を回避できる。
相手が断ったり、自分の望まない行動を取ったとしても、「相手には相手の理由がある」と受け入れられる可能性(余白)を持つこと。
搾取に加担する集団的な選択に、拒否を表明する勇気を持つこと。
レベル3 共感による修復・構築
…相手の欲求に瞬間的に同調できることを知り、その作用を理解し、関係性の修復や構築ができる。
この講座では時間内にここまで到達しませんでしたが、哺乳類には瞬間的に他者の感情に同調できる「共感」という能力があります。共感は非常にパワフルなもので、心の痛みを手放せたり、信頼関係を瞬間的に生成したりもできます。
説明は難しく長くなるので、ここでは割愛。
自分たちが加害側であるという認識や、ごく習慣的な振る舞いにも暴力が内包されていることなど、なかなか受け入れたいものではありません。
しかし、「受け入れ難いからないことにする」のと、「受け入れ難いが、あることは知っている」のと、その差は天と地ほど離れたものがあると私は思うのです。
私は、このNVC回を通して皆さんに「まず、あることを知ってほしかった」というのが、この講座の設計意図の2つめです。
2. NVC回 : 当日の様子
プライベートな話題も多く、ここではその詳細を挙げることはしません。
安納献さん、鈴木重子さんのお人柄もあり、一歩ずつそれぞれが理解へ向けて進んでいく、という時間だったと思います。

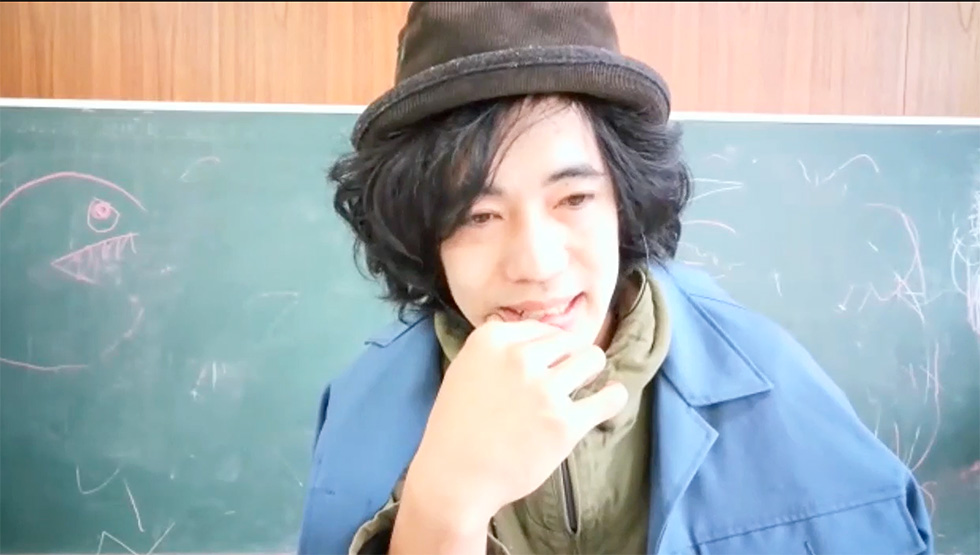

[執筆: テンダー]
[事業担当: 室中 直美]
このオンライン講座は、2021年2月から2023年3月まで実施しました。
▶︎ 全講座のスケジュール
▶︎ これまで実施した講座のレポート
– 第1回「アルミ缶を使い倒そう」
– 第2回「棒と板だけで火を起こそう」
– 第3回「3D設計と3Dプリントを覚えて、必要なものを作ろう」
– 第4回「雨水タンクを作って、水を自給自足しよう」
– 【前編】 第5回「システム思考を身につけて『しょうがない』を乗り越えろ!」(テンダーさん執筆)
– 【後編】 第5回「システム思考を身につけて『しょうがない』を乗り越えろ!」(テンダーさん執筆)
– 【前編】 第6回「その辺の草からロープを作ろう。ロープができれば暮らしが始まる」
– 【後編】 第6回「その辺の草からロープを作ろう。ロープができれば暮らしが始まる」
– 秋の特別編「その辺のもので生きるための心の作法 〜『正しさ』を越えて」 (テンダーさん執筆) new!
– 第7回「プラごみから必要なものを作る」
– 第8回「キッチンで鋳造を始めよう!」(テンダーさん執筆) new!
– 【前編】第9回「鉄工を身につけて強力なストーブを作ろう」(テンダーさん執筆)
– 【後編】第9回「鉄工を身につけて強力なストーブを作ろう」(テンダーさん執筆)
– 第10回「きみのためのエネルギー。 実用パラボラソーラークッカーを作って太陽熱で調理する」(テンダーさん執筆) new!
– 【前編】 第11回「交渉を学び、こころざしを護る」(テンダーさん執筆)
– 【後編】 第11回「交渉を学び、こころざしを護る」(テンダーさん執筆)
– 【前編】 第12回「生き物の輪に戻るためにドライトイレを作ろう」(テンダーさん執筆)
– 【後編】第12回「生き物の輪に戻るためにドライトイレを作ろう」(テンダーさん執筆)
– 第13回「当たり前を変えよう、大切なものを守ろう」(テンダーさん執筆) new!
事業データ
「その辺のもので生きるための心の作法 〜『正しさ』を越えて」(テンダーさんの「その辺のもので生きる」オンライン講座【秋の特別編】)
2021年11月28日(日)
オンライン
TJF
◆ 鈴木重子さん
CNVC(Center for Nonviolent Communication)認定トレーナー、ヴォーカリスト、アレクサンダー・テクニーク教師、文筆家
◆ 安納献さん
CNVC(Center for Nonviolent Communication)認定トレーナー、アレクサンダー・テクニーク教師、通訳
テンダーさん(環境活動家、生態系の再生と廃材利用のための市民工房「ダイナミックラボ」運営)
https://sonohen.life/
中学生〜大人 62名(日本、イタリア、オーストラリア、スイス、フィリピンから参加)
堀江真梨香さん
